8年間の新聞記者生活を経て映画の世界に飛び込んだ奥村盛人監督の初長編作『月の下まで』を上映中の渋谷ユーロスペースで9月15日に、ゲストに『Shall we ダンス?』『それでもボクはやってない』などの周防正行監督を迎えてのトークイベントが開催されました。
『月の下まで』は、高知新聞社を退社したのち映画美学校で学んだ奥村監督が資金集めから独力でおこない製作した作品。
周防監督は『月の下まで』について「切実なものが伝わってくる。それがぼくにとって一番いい映画で、なにがいい映画というと、価値観が揺さぶられるとか、新しい表現に驚くとか、観る前と観たあとでなにか自分が変化するのがいい映画だと思うんです。この映画は真摯に人の心に突きつけてくるものがあっていいなって思いました」と感想を述べ、奥村監督の「ほとんど勢いと言うか、撮りたいという気持ちと、最初のスタートをしなければいけないというある種の切迫感みたいなのがあって、自分自身を発奮させて突き進んでという感じでした」という答えに「そういう気持ちを実現するのはいまの社会で難しいことだと思うので、これから先のことも含めて“映画を作る”といういまの気持ちを持ち続けてほしい」とエールを送りました。
新聞記者出身の奥村盛人監督、影響を受けた周防正行監督とトーク 『月の下まで』トークイベント

劇場ロビーにて、トークゲストの周防正行監督(左)と奥村盛人監督
話題は周防監督の代表作のひとつ『それでもボクはやってない』へと移り、周防監督は「初めて怒りがもとになっていた映画だった。それまでの映画はどこか素材に対する共感が根っこにあるんだけど『それでもボクはやってない』は“日本ってこんなんでいいのかよ?”ということをほんとに思って、その怒りで“裁判なんてこんななんだぜ”ということを伝えないとマズいと、ある種の使命感があって、それはそれまで映画とは違って、まあダークサイドですよね」と製作の動機を説明。奥村監督は「当時まさに事件担当の記者をしていて公判も見ていたし、刑事事件の問題点なんかもずっと見ていたので、(映画を)観た瞬間に“やられた!”というか、ある種それがぼくを映画にいざなったひとつの要因と言えるかもしれないくらいのものを与えられたんです。周防さんによって(人生を)変えられたかもしれない」と、同作品から受けた大きな影響を語りました。
さらに周防監督は同作品の取材の過程で司法記者クラブの記者への取材を拒否されたというエピソードを紹介し「裁判が悪いのって警察とか検察、裁判官とか弁護士だけが悪いんじゃなくてマスコミの責任もあって、突き詰めていくと“俺じゃん、そういうことを許している一般市民じゃん”という話にならざるを得ない。そこは苦しいところで『それでもボクはやってない』だけでは終われない問題なので、これから先も作りたいんと思うんですよね」と、ふたたび裁判を題材とした映画を撮る意図があることを明かしました。
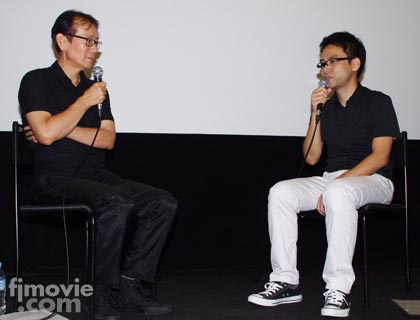
トーク中の周防監督(左)と奥村監督。現在新作仕上げ中の周防監督は,トーク終盤に奥村監督に「ぜひ見学に来てください」と言葉をかけていました
トークはいままさに編集中だという周防監督の新作『舞妓はレディ』の話題から周防監督の編集術、そして周防監督の過去の作品を生み出した取材についても広がり、周防監督は奥村監督に「自分が8年間一生懸命働いていた世界を客観的に見ること、これは最高の取材源というか、あなた自身が経験した8年で映画が撮れる。自分が経験したことを振り返ってみるのはすごく貴重だと思う。ぼくも観たいです、高知の事件記者」と、自身の経験を映画のもとにすることをアドバイスし、奥村監督の「報道メモというのがあってですね」という言葉に「俺作っちゃうよ(笑)」とのジョークも。奥村監督は「どうやって次に向かっていけばいいのかなっていうのは悩みながらやっているんですけど、いまの監督のお言葉で強く」と、意欲を見せました。
奥村監督が学生時代や新聞記者時代を過ごした高知県を舞台に、漁師の男性と障害を持つその息子を中心に現代の日本に存在するさまざまな人間模様を描いた『月の下まで』は、9月14日(土)より27日(金)までユーロスペースにて公開、ほか全国順次公開されます。
