『神奈川芸術大学映像学科研究室』坂下雄一郎監督インタビュー
 奥田明は神奈川芸術大学映像学科に勤める助手。ある日、学生による学科備品の盗難事件が発生するが、事件が明るみに出るのを怖れる教授陣は事件を「隠蔽」することを決定。奥田は隠蔽のためのウソの報告書作りを命じられる……。
奥田明は神奈川芸術大学映像学科に勤める助手。ある日、学生による学科備品の盗難事件が発生するが、事件が明るみに出るのを怖れる教授陣は事件を「隠蔽」することを決定。奥田は隠蔽のためのウソの報告書作りを命じられる……。
一見、劇映画とは思えないタイトルの『神奈川芸術大学映像学科研究室』は、東京藝術大学大学院映像研究科映画専攻の修了作品として制作された作品。架空の大学“神奈川芸術大学”を舞台に、教授陣に振り回される助手の姿を通して、組織の理不尽さがシニカルに、そしてコミカルに描かれていきます。
この作品を作りあげたのは、大阪芸術大学映像学科を卒業後、同大学助手として勤めたのち東京藝大大学院へと進学した坂下雄一郎監督。大阪芸大で大森一樹監督に、東京藝大大学院で黒沢清監督に師事した経歴を持つ期待の新鋭です。
大学院の修了制作でありながら“大学組織の理不尽さ”を描くという、作品のあり方自体もシニカルに見える『神奈川芸術大学映像学科研究室』は、SKIPシティ国際Dシネマ映画祭2013長編部門審査員特別賞受賞を経て、一般公開を迎えます。まさに大学から映画館へと放たれる異色作はいかにして生まれたのか? 坂下監督にお話をうかがいました。
坂下雄一郎(さかした・ゆういちろう)監督プロフィール
1986年生まれ、広島県出身。大阪芸術大学映像学科を卒業後、同大学の助手となる。2年間助手として勤めたのち、東京藝術大学大学院映像研究科映画専攻に第7期生として入学。在学中から助監督として現場経験を積みつつ、短編『ビートルズ』(2011年)で第22回ゆうばり国際ファンタスティック映画祭2012でファンタスティック・オフシアター・コンペティション部門北海道知事賞を受賞。大学院修了制作作品『神奈川芸術大学映像学科研究室』がSKIPシティ国際Dシネマ映画祭2013長編部門で審査員特別賞を受賞し、同映画祭の劇場公開支援プロジェクト「SKIPシティ Dシネマプロジェクト」第4弾作品に選出され一般公開が決定する。2013年3月東京藝術大学大学院修了。ほかの作品にオムニバス『らくごえいが』の1編「猿後家はつらいよ」(2013年)など。
「“建前としてはやっちゃいけないけど、ほんとはやっている”みたいなことを取りあげたら面白いかな」
―― 『神奈川芸術大学映像学科研究室』は、大学の映像系の学科が舞台で助手が主人公というのが面白い設定だと思いました。この発想はどのように生まれたのですか?
坂下:この作品はもともと大学院の修了制作として作ったんですけど、修了制作は特に企画の制限もなく、大学に「こういうものを作ります」と言ったら自由に作らせてくれるもので、東京藝大の大学院に入る人たちはみんなこれを撮るために入ってきているんですよ。それで、自分が撮るとなったときにいろいろ企画を考えたんですけど、自分が撮る理由が掴めないというか「この企画って自分じゃなくても撮れるなあ」というものが多かったんですね。「じゃあ自分が撮る理由ってなんだろう?」と考えたら、自分が経験したことを企画にすれば撮る理由になるんじゃないかと思ったんですね。それで自分の人生を鑑みてみて、ぼくは大阪芸大を卒業したあと2年間助手をやっていたので、自分の人生の経験からなにかしら映画の企画ができるとすれば助手の経験だなと思って、そこから考えたんです。
―― この作品は、学内で起きた事件を隠蔽するというのがストーリーの軸になっていきますが「隠蔽」という題材を取り入れた理由というのは?
坂下:助手をやっていた当時の経験が大きいんですけど、やっぱり働いていると、ちょっとしたことだったら悪いことってしがちだと思うんですよ。「ほんとはよくないけど、まあちょっとやっちゃおうか」みたいことが多いなあと思っていたので、特別なことというよりは、けっこう日常的なこととして「建前としてはやっちゃいけないけど、ほんとはやっている」みたいなことを取りあげたら面白いかなと思って、やってみました。
―― いまは、企業や公的機関などの隠蔽がニュースとなることも多いですが、特にそういう社会的な話題を取り入れようというわけではなかったのですか?
坂下:そういうところから発想するというよりは、自分の働いていた環境からですね。こういうことが起きたら隠しちゃうのも不自然ではないだろうというか、表に出ないだけでそういうことって実際にはたくさんあるんだろうと思っていますし、むしろ普通のこととしてサラッと描いたほうがいいなと。それから、映画ですし、隠したほうが物語としては面白くなるだろうという面もありました(笑)。
―― 監督ご自身の経験がもとになっているというお話がありましたが、実際にどの程度が実体験なのでしょうか? 差し支えない範囲で(笑)。
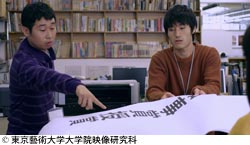
『神奈川芸術大学映像学科研究室』より。垂れ幕作りにいそしむ主人公・奥田(演:飯田芳・右)と、同僚の斉藤(演:前野智哉)
坂下:まあ、学生が備品を盗んでそれを隠蔽するという事件はフィクションですけども、周りのもろもろの描写はだいたいが経験したことですね(笑)。先生方の飲み会の場所を決めるとか、学生の作った作品が受賞したから「お祝いの垂れ幕を作っておいて」と言われて作るとか、だいたい経験しています。
―― 学生がロケ先でトラブルを起こして謝りに行くというようなエピソードもありましたけど、ああいうことも実際にあるんですか?
坂下:あれはよくありますね(笑)。苦情が来たりとか。
―― 作品を拝見して思ったのですけど、娯楽映画のジャンルとして「内幕もの」ってありますよね。1本の映画が作られる裏側とか、テレビのニュースショーの裏側とか。『神奈川芸術大学映像学科研究室』は、大学が舞台というのは独特ですけど、内幕ものという意味では、伝統的な娯楽映画の系譜にある作品なのかなと思いました。
坂下:そうですね、もともとそういう路線というか方向性で作ろうとしていたんです。最近の作品で言うと『ハッピーフライト』(2008年/矢口史靖監督)とか、ああいう路線で作ろうというのは決めていました。大学を舞台にした時点で、あまり知られていない部分を強調しようというのは決めてたんです。
―― 作品のタッチとして、参考にしたというか、目指していた作品があれば教えてください。
坂下:『スーパーの女』(1996年/伊丹十三監督)ですね。それから、いま言いました『ハッピーフライト』とか、あとは『シコふんじゃった。』(1992年/周防正行監督)とか。
―― 『スーパーの女』というのはすごくわかる感じがします。日本の作品をイメージされていたんですね。
坂下:そうですね、日本の映画で内幕ものですね。
―― 大学院の修了制作で、大学のあんまりよくない面を描いた作品を作るというのは、作品のあり方自体もシニカルな感じがしたのですが、監督はそういう意図はされていたのですか?
坂下:そこまでなかったんですよね。大学院自体がけっこう自由で、学生のやろうとしていることを拒否したりせずにやらせてくれるようなところなんですよ。撮影前に「こういうのを撮ります」ってシナリオを出すんですけど、特になにも言われませんでしたし(笑)。やっぱり、自分の経験したことをもとにして考えていくとこういう内容になっちゃって、さわやかな話にはならないなって(笑)。ただ、できあがったあとに先生に「最後に“フィクションです”って入れてね」と言われて、入れました(笑)。
「あまり内面的なものは伝えないんです。直してもらうときは“仕草とか行動をこういうふうに”と」
―― 作品を拝見して、主人公の奥田ならこういう経歴なのかなとか、学科長の森田さんなら映画監督出身なのかなとか、劇中では描かれていない登場人物のバックグラウンドを感じました。そういう人物の背景は、かなり作りこまれていたのでしょうか?
坂下:だいたい全員にモデルがいるので、それに似せつつちょっと誇張して書いたんです。(大阪芸大の)学科長は大森(一樹)さんですから、別に映画の学科長のようにヤクザみたいな人ではなかったんですけど(笑)、最近は映画監督の方が大学の映像系の学科の学科長になることが多いと思うので、なんとなく昔気質ではないですけど叩きあげの監督という感じで、そしたらちょっと怖い人かなあと考えたりとか(笑)。
―― それは、演じる俳優さんにも伝えられたのですか?
坂下:そんな細かくは言っていないんです。現場で聞かれたら、学科長だったら「映画監督を経てこの学科の学科長になっています」とか、ザックリとした経歴を言うくらいですね。
―― それで人物があれだけ実感にあふれているというのは、キャスティングの力も大きかったのでしょうか?
坂下:それは大きかったと思います。今回はすごく巡りあわせがよかったというか、みなさん知り合いに紹介してもらった人ばかりなんですよ。候補から選ぶというよりは、ほぼみなさん最初に紹介してもらった人たちで、なんとなく顔やら声やらイメージがいいなと思って、すぐ決まったんです。
―― たとえば主人公の奥田であれば、どんな俳優さんを求めていらっしゃったのでしょうか?
坂下:ふてくされた態度が魅力的な人がいいんじゃないかなと思っていました。やっぱり、知り合いに脚本を読んでもらって「これに合う人いないですか?」って聞いたのが大きいですね(笑)。
―― 一番キャスティングが大変だった役というと、どなたでしょう?

『神奈川芸術大学映像学科研究室』より。奥田と学科長の森田(演:宮川不二夫・左)、准教授の竹内(演:高須和彦)
坂下:やっぱり、主役はほんとに不安というか、始まるまで「大丈夫かな?」という気はしていましたね。今回は前野(朋哉=助手・斉藤役)さん以外はほとんどの人が初めてぼくの映画に出ていただいたので、やってみないとわからない部分がけっこう大きくて「どうなるんだろう?」と思いつつやっていた記憶はあります。
―― 奥田ってあんまりわかりやすいキャラクターではないですよね。演じる飯田芳さんにはどんなふうにキャラクターを伝えたのでしょうか?
坂下:ぼくは、あまり内面的なものは伝えないんですね。基本的にまずやってもらって、直してもらうときは、心境というよりは「仕草とか行動をこういうふうに直してもらえますか」という感じですね。あとは、ほぼ自伝みたいなものなので(笑)、ほかの役よりは「こういうときはこういう感じです」と伝えるのは容易にできたと思います。
―― 具体的に伝えるというのは、ほかのキャストのみなさんについてもそうなのですか?
坂下:そうですね、基本そうです。
―― では、監督の頭の中にそれぞれの人物の喋り方とか動き方とか、そういうイメージができあがっていると。
坂下:そうですね、ただ、それをその通りにやれるかというとそういう問題でもないので、そこはすりあわせていくというか、その人にあった言い方で言ってもらえるのが一番いいと思うので、あんまり自分のやり方は押しつけないように、その人のできる方向性でやっていました。
―― 先ほど前野朋哉さんのお名前が出ましたけど、この映画はメインとなる隠蔽の話と、前野さん演じる斉藤が中心となる学生の上映会の話が、ほぼ無関係に進んでいきますね。あれは面白いですね。
坂下:最初の企画では前野さんのパートはなかったんです。だけどシナリオを人に見せたときに、あのパートを省くと全部が奥田目線での話になってしまうので、もう少し俯瞰で見られるような構成にしたほうがいいじゃないかという意見をもらったんです。もうひとりの人物のもうひとつの出来事があったほうが、より多面的というか幅が広がるのではないかということで、あの話を入れました。
―― 刑事ものの映画なんかでも、メインの事件以外に別の事件が起こって並行して描かれると世界が広がりますよね。そういう作品を連想しました。
坂下:本当にそういうイメージですね。それから、単純に前野さんが大学のときからお世話になっている先輩なので、出ていただくんだったらなにかしら目立つ部分を作ったほうがいいのかなということもありました(笑)。
―― あの上映会の話というのも、やはり監督ご自身の経験が入っていらっしゃるのでしょうか?
坂下:そうですね、学生のときには上映順で揉めたりとかしましたし、助手になってからはそういう上映会をまとめる立場にいて、人が全然いなかったときとかありましたね。ぼくはあんなに動かずに、放置してましたけど(笑)。
―― あそこで学生があんまり上映会に熱心じゃないというのが面白いなあと思って、冷めてるというか、けっこう情熱のない学生が出てきますよね(笑)。
坂下:アハハハ(笑)。そうですね、冷めてるというか、大阪芸大にいたときは人数が多かったんですね。一学年に100人くらいいたので、やっぱりいろいろですね。映画を作ることより、もう就活に気が向いてる子とかもいますし、学校に来なかったりする子とかもいるし、そこは様々ですよね。みんながみんなが情熱を持ち続けるわけではないんだなと(笑)。
「作家性より、周りに受け入れられるものを作るほうが向いてるのかなと思って作った記憶はあります」
―― 監督は、まず大阪芸大で学ばれているんですよね。映画を学ぼうと思ったきっかけはなんだったのですか?
坂下:ぼくは高校が通信制なんです。「学校行きたくないな」と思いつつも「高校くらい行っとかないかんな」ということで通信制に行って、通信制って提出物さえ出してれば月に2回くらい行けばいいんですよ。それでバイトを始めて、お小遣いというかお金がある程度貯まったのでビデオデッキを買って、近くにレンタルビデオ店があったのでそこに通って映画を観るようになったんです。そのときはのめり込むというほどではなくて、ほかに音楽も聴いたりしてましたし趣味のひとつだったんですけど、高校が終わるくらいのときに「さすがに大学は行っておかないとまずいんじゃないか」と思いだしまして、そこから受験勉強を始めると入れる大学が限られてきて、大阪芸大って推薦だと学科試験がないんですよ。映像が好きになりかけていたし「これだったら行けるかな」と思って受けたら受かったんです。「じゃあ行こう」と(笑)。
―― それで大阪芸大で勉強されて、卒業後に助手になられたのはどういう経緯で?
坂下:それも、4回生の12月くらいに「なんも決まってないなあ、まずいなあ」と思っているときに掲示板に助手募集の張り紙が貼ってあって、時給とかも書いてあって、意外とよかったんですよ。それで応募したら受かりました(笑)。非常勤で、まあバイトに近いようなものですね。
―― そして助手として2年勤められたあとに、東京藝大大学院映像研究科に進学なさるわけですね。
坂下:それもですね、助手の契約期間が決まっていて「そろそろ終わるなあ、まずいなあ、どうしようかなあ」と思ってたんですよ(笑)。やっぱり映像の仕事は東京が多いので、みんなけっこう東京に行ったりしてたんですね。でも、いきなりフリーで行くのは怖いし、かと言って就活もしていなかったし「学校に行ったら東京に行く口実になるのかな」みたいな面がありまして、東京藝大って国立なんで学費が安いんですよね。「あ、ここかな」と思って、試しに受けてみたんです。そしたら受かって「行こう」って(笑)。
―― お話をうかがっている限りだと、あまり積極的ではない方向で進路を決めていらっしゃるというか(笑)。
坂下:アハハハ(笑)。そうなんです、ちょっとそんな部分がありまして、受かるかどうかわからなかったんですけどね。
―― 大阪芸大も東京藝大大学院も、たくさんの映画人を輩出していますが、両方で学んだ方はあまりいらっしゃらないと思うので、監督からご覧になったそれぞれの特色があれば教えてください。
坂下:大きい違いは、東京藝大の人たちはけっこうシネフィルで、大阪芸大の人たちは映画をあんまり観ないということですね(笑)。大阪芸大ってすごい田舎にあるので、一番近くの映画館に行くにもたぶん往復で1000円くらいかかるんですよね。そういう事情もあって、意外と映画を観ない学生が多いんですね。
―― もちろん学部と院の違いはあると思いますが、学ぶ内容でそれぞれの特色を感じられたところはありますか?

坂下:大阪芸大は、シナリオなり作品なりを作って、いろいろ言われることで学ぶというのが大きいんです。教授の人たちもけっこうキツ目に「おもろない」とか「これは時間の無駄や」みたいなことを言うんですけど、それを経て学ぶものが多かったりするんです。東京藝大は、映画論じゃないですけど講義からの学びの面が多かったですね。あとはまあ、東京藝大は学生が作品を作るときに予算が出るのでキッチシやろうという風潮があるんですけど、大阪芸大は自腹なんで無茶しがちです(笑)。
―― 無茶しがちだから、苦情が来るようなことをやってしまうと(笑)。
坂下:そうですね、いろいろぶっ壊したり(笑)。もう大阪芸大周辺の道路とかは警察に言っても許可が下りなくなってます(笑)。
―― 大阪芸大では大森一樹監督、東京藝大大学院では黒沢清監督にご師事されたんですよね。両監督についてなにかエピソードがあればお願いします。
坂下:よく覚えているのは、大阪芸大で助手を辞める前に大森さんに「今度、東京藝大を受けるんですよ」って言ったら「あそこは大阪芸大の人間は採らへん」って言われて(笑)。たしかにいままで監督では誰も受かっていなかったんですよね。「ああ、そうなんだ」って思って、それで受かってから「受かりました」と言ったら「東京藝大も落ちたもんや」って。もちろん冗談ですが(笑)。
―― そういう大学での経験も活かされた作品が一般公開を迎えるわけですが、作る時点で一般の観客の方々に観てもらうことは意識されていたのでしょうか?
坂下:そうですね、ぼくは東京藝大に入ったころは、周りがシネフィルばかりなので「自分もそういう作品を観てみよう」といろいろ観てみたんですけど「こっちではないんだな」と思ったんです。東京藝大ってけっこう作家性を大事にする大学なので、一般向けというよりは、どちらかというと自分の描きたいものを描くという風潮というか指導があるんですね。でも自分はそういう方向よりは、自分を殺してでも周りに受け入れられるものを作るほうが向いてるのかなと思って作った記憶はありますね。
―― 一般公開に先駆けて映画祭で上映されていて、そのときに初めて一般の方に観てもらったわけですよね。そのときのお気持ちはいかがでしたか?
坂下:「わかるわかる」みたいな感想をもらったんですね。特に働いている方からはそういう感想をもらって、そこは意外でしたね。自分では大学の中で完結しちゃうような話なのかなと思っていたので。
―― ちょっと気が早いかもしれませんが、今後こういう作品を手掛けてみたいというのがあればお願いします。
坂下:個人的には、実在の事件とか出来事がもとで、その裏でフィクションのなにかしらの話があったりするのがいいですね。ぼくは『グッバイ、レーニン!』(2003年・独/ヴォルフガング・ベッカー監督)とかが好きなんです。ああいう、歴史的な事実も織り交ぜつつ、フィクションの人物の行動をというのが好きですね。
―― やはり今後の作品も、テイストとしては『神奈川芸術大学映像学科研究室』に近いような、コメディ系のものになるのでしょうか?
坂下:そうですね、あまりコメディって意識してはいないんですけど、個人的には明るい映画が好きなので、暗い映画を撮っているとつらいじゃないですか(笑)。気持ちが落ちてくるんで、撮ってて楽しい明るいほうがいいなあと(笑)。ただ、最近はあんまり「自分はこうだからこういうことしかやらない」と決めつけないほうがいいなと思っているので「これは自分の中には全然ないなあ」と思うようなものでもやるようにしています。
―― 最後に『神奈川芸術大学映像学科研究室』の公開を前にしたお気持ちと、ご覧になる方へのメッセージをお願いします。
坂下:まあ、観てもらうしかないというか、観てもらわなければ良いも悪いも言われないですから、観てもらったからにはもう真摯に感想は受け止めようと思っています。決して規模の大きい作品ではないですけど、そういう映画もそんな悪いものでもないんだぞと(笑)。そういうことを感じてもらえたらいいですね。
(2013年12月24日/ソニーPCLクリエイションセンターにて収録)

神奈川芸術大学映像学科研究室
- 監督:坂下雄一郎
- 出演:飯田芳 笠原千尋 前野朋哉 ほか
2014年1月25日(土)より新宿武蔵野館ほか全国順次公開
