脳波を同期させる未認可の実験に取り組む研究者の青年と、彼に惹かれ協力する女性研究者。ふたりは、認知症となった青年の母親を脳波同期実験により治療しようと試みる。その実験がもたらすものとは……。
「同期させるもの」という意味を持つ『シンクロナイザー』と題された万田邦敏監督の新作は、往年のSFやスリラー映画を思わせる手法を用いながら、主人公とその母親、ヒロインという3人の男女の愛憎を描いた作品となっています。
高いエンターテイメント性を持った作品であると同時に、映画自体が既存のジャンルを越えた意欲的な「実験」にも感じられる『シンクロナイザー』。特異な魅力を放つこの作品はどのように生まれたのでしょうか?
万田邦敏(まんだ・くにとし)監督プロフィール
1956年生まれ、東京都出身。立教大学在学中から映画制作をおこない、黒沢清監督の『ドレミファ娘の血は騒ぐ』(1985年)に脚本・助監督として参加。企業PRビデオやテレビドラマの演出、雑誌「カイエ・デュ・シネマ・ジャポン」での映画評執筆などの活動を経て1996年に『宇宙貨物船レムナント6』で劇場作品初監督。ほかの監督作に『UNloved』(2002年)、『ありがとう』『接吻』(2006年)など。また、立教大学現代心理学部映像身体学科教授、映画美学校フィクション・コース講師をつとめ、映画美学校高等科コラボレーション作品として『イヌミチ』(2013年)を監督している。
「『ザ・フライ』を最初に観たときから、いつかこんな映画を撮りたいなと思っていた」
―― 最初に『シンクロナイザー』で物語の中心となっている「脳波の同期」というアイディアがどのように生まれたのかをお聞かせいただけますか?
万田:それがね、よく覚えていないんですよ(笑)。脚本を作っていく段階で、脚本家の小出豊くんが「ブレイン・マシーン・インターフェイス=BMI」というネタを持ってきたんです。それまでに脳波という話が出ていたかどうかはよく覚えていないんですけど、いずれにせよ小出くんが「これは使えるんじゃないんですか?」とBMIというネタを持ってきて、そこから本格的に「脳波を同期していく」という話を作っていくことになったんじゃないかと思います。
―― 監督は、もともと脳のメカニズムなどに興味はお持ちだったのでしょうか?
万田:ぼくは全然ないです(笑)。
―― そうすると、小出さんがBMIというアイディアをお持ちになられたときに、それを取り入れようと思ったポイントはどんなところだったのでしょう?
万田:なんでしょうかね。BMIって、体の不自由な方の脳波を測定してコンピューターに送って、コンピューターが電気信号に変えて、本人の手足の代わりにコンピューターにつながった機械が動くというものですよね。普段、人間の体というものは脳の神経が手足を動かすわけですけど、自分の意志が1回機械に送られて、その機械から別の信号になって別のものを動かすということに興味を持ったんでしょうね。もし、それが勝手に動き出したらどんなことになっちゃうんだろうとか、あるいは逆に動く機械の側からなにかが送られてくるとどうなるのとか、そういう発想があったんだと思うんです。そこから「コンピューターを介して他人の脳波とつながったらどんなことが起こってしまうのだろう?」みたいな発想の流れがあって、そこに興味を持ったのかもしれません。
―― 脳波というアイディアを小出さんがお持ちになる以前の、企画の出発点ではどのようなストーリーを考えられていたでしょう?

『シンクロナイザー』より。脳波を同期させる実験に没頭する主人公・長谷川高志(万田祐介・右)と、彼の実験に協力する木下萌(宮本なつ)
万田:そこもいまとなってはけっこうあやふやな記憶なんですよね(笑)。まず最初は、老化防止を研究している若い研究者がいて、他人の老化を防ぐことに意欲を燃やしているんです。それで、認知症というアイディアがその時点であったかどうかはあやふやなんですけど、お母さんの老化を防ぐ研究をしていて、老化防止の特殊な新薬みたいな発見をして、すぐに人間に使いたいけどそれはできないので、法や倫理を超えて実験にのめり込んでいく。のめり込んでいくと自分のダークサイドみたいなものが開発されてしまって、善良な研究者だったのがお母さんとの関係の中でとんでもないことが起こっていくみたいな、そういう大まかなストーリーラインでしたね。
―― そうすると、新薬と「脳波の同期」という違いはあっても、完成した作品は骨子としては最初のストーリーラインから大きくは変わっていないのでしょうか?
万田:ただ、できあがった作品では主人公とお母さんとの深い結び付きみたいなものが出てくるんだけど、最初はそれはなかったんですよ。できあがった作品ではヒロインとして主人公に協力する女性の研究者がいますよね。最初は彼女が主人公の兄嫁で、主人公と兄嫁との不倫みたいなことも考えていたんです。その中で、お母さんも含めた3人の関係みたいなことを思いついてきて、脚本あるいはプロットのやり取りをする中で、やるんだったらどんどん深くみたいなことで、ああいう深い結び付きみたいなところに流れていったんだと思いますね。
―― 全体的にかつてのSFやジャンル映画のテイストを感じたのですが、それは意図をされていたのでしょうか?
万田:どっちかというとぼくは新しいものより古いもののほうが好きなので、知っている人は映画を観るとすぐわかるだろうけど、特に意識したのは、(デイヴィッド・)クローネンバーグの『ザ・フライ』(1986年・米)ですよね。これはもう最初に観たときから、いつかこんな映画を撮りたいなと思っていたので『ザ・フライ』は確実に下敷きにしましたね。
―― 個人的に「怪奇大作戦」(※1)を連想したのですが、それは意識されていましたか?
万田:それもよく言われるんですけど、冒頭のクレジットが出るタイトルの印象じゃないかと思うんですよね。「怪奇大作戦」は、ぼくよりもうちょっと下の世代の、監督で言うと塩田明彦とか高橋洋とかは熱狂的なファンなんですが、ぼく自身はそれほど思い入れはなくて、ただあの世界観は嫌いではないし、何本かの作品は面白いなと思います。ぼくはむしろ「ウルトラQ」(※2)ですよね。あの「ウルトラQ」という文字がキューンと回るタイトルは子供心に衝撃的で、なんだか変なものを見せられているという感じがあったので、だから「怪奇大作戦」もその系統を色濃く受け継いでいるんでしょうし、ぼくの中には「ウルトラQ」の想い出みたいなものがずっと残ってたんだということを、今回改めて思いましたね。
- ※1:1968年より69年にかけて放送された円谷プロダクション制作のテレビドラマ。架空の犯罪捜査研究所・SRIのメンバーがさまざまな怪奇事件の謎を解き明かす1話完結のストーリーで全26話が放送された。2007年には「怪奇大作戦 セカンドファイル」、2013年には「怪奇大作戦 ミステリー・ファイル」と2度にわたりリメイク作品が製作されている。
- ※2:1966年に放送された円谷プロダクション初となる全28話のテレビドラマ。毎回多彩な怪獣や宇宙人などが登場する内容は大人気となり、巨大ヒーローが登場する「ウルトラマン」「ウルトラセブン」へと続いていく。リメイク作に映画『ウルトラQザ・ムービー 星の伝説』(1990年/実相寺昭雄監督)、テレビシリーズ「ウルトラQ dark fantasy」(2004年)、「ネオ・ウルトラQ」(2013年)がある。
「日常的に使っているセリフとかリアクションみたいなものをなるべく書かずにやっている」
―― 『ザ・フライ』を意識されていたということですが、作品作りの過程でジャンル映画的なテイストというのは意図して入れていくものなのでしょうか? あるいは自然に出ている部分もあるのでしょうか?
万田:どうなんだろうね、ジャンル映画としてという意図は特になかったと思いますけど、ぼくの作るものは、今回のような物語ではないにしても大概は古めかしいものになるんです(笑)。いわゆる昔の日本映画のテイストみたいなことになるんですけど、それは意識してやっているんです。芝居の質みたいなところでなるべく現代性を持ち込まないし、脚本のセリフのひとつひとつも現在ぼくらが日常的に使っているセリフとかリアクションみたいなものをなるべく書かずにやっているので、そうすると必然的に昔の日本映画のテイストが出るし、昔の日本映画というとジャンル映画ということになってくるので、そのテイストが出てきているんだろうなというふうに思います。あえてぼく自身が特にジャンルを意識してやっているというわけではないんです。
―― お芝居の話が出たところでキャストの方々についておうかがいしたのですが、メインキャストの方々はどのように決まっていったのでしょうか?
万田:主演の俳優は万田祐介という、これはぼくの甥っ子で舞台のほうを中心に芝居をやっていて、せっかくぼくが作る機会があったので彼に出てもらいたいなと思ってオーダーをしました。ヒロインの宮本なつさんは、万田祐介とは違って映像作品に出ることが多い役者さんで、ぼくは彼女が主演している『ひとまずすすめ』(2014年/柴田啓佑監督 ※3)を観ていたんですよ。それで印象はあったし、甥っ子と知り合いだというので話がしやすいかなみたいなこともあって、お願いをして決まりました。主演とヒロインのふたりはわりと早くに決まっていましたね。それから中原翔子さんに出ていただいているんですけど、中原さんとは前からの知り合いでもあって、ぼくの映画に出てほしいなとずっと思っていたので中原さんもすぐに決まって、大塚怜央奈さんと主人公のお母さん役の美谷和枝さんはオーディションみたいなことをやらせていただいて決めています。今回は、みなさんわりとすぐに「あ、この人はいいな」という方に出会えて、実際にものすごくよかったですね。
―― 万田祐介さんには、主人公の長谷川高志という人物を演じる上でどのようなことを求められたのでしょうか?

『シンクロナイザー』より。長谷川高志(万田祐介・右)に厳しい言葉をかける研究所の主任(古川博巳)
万田:あんまりトータルで「この人はこういう人で、ああいう人で」というようなことはたぶん言っていないですね。脚本を読んで、想像できる範囲で想像してくれればいいかなと思っていたので、その辺は長谷川にしても、宮本さんがやった萌にしても、特にはあまり言っていないですね、それよりも具体的に芝居の場で「こういうふうに動いて、ああいいうふうに動いて」というのはかなり細かく指示はしています。
―― キャストでもうおひとりお話をうかがいたいのが研究所の主任役の古川博巳さんで、役柄も含めて「ジャンル映画らしさ」を醸し出していたように感じました。
万田:いわゆる敵(かたき)役ですよね。ぼくは物語映画を作りたいと思っているので、そうすると主人公に敵対する人物がどうしても必要になってきて、その人がいいと映画自体がものすごくよくなるんですよね。『ザ・フライ』はその敵役が少し弱いと思っているんです。それで、今回『シンクロナイザー』の敵役のキャスティングをするときに、古川くんはとってもわかりやすいマンガのような顔形をしているので(笑)、そういう意味で敵役にいいかなとお願いをしました。古川くんは映画美学校アクターズ・コースの出身で、ぼくの『イヌミチ』(2013年)にも出てもらってうまく演じてくれたし、その後も美学校で短いアクターの講座があったときに来てくれて何度か芝居をしてもらったりしていたんですよ。今回はそのほかの研究所の所員たちもみんな美学校の講座の関係の子たちに来てもらって、脇役なんだけどみんなそれぞれ自分の役をきちんとこなしてくれていたなというのはありますね。
―― 『イヌミチ』のお話が出ましたが、今回『シンクロナイザー』の後半では日本家屋を中心に話が進んでいって、やはり日本家屋が出てきた『イヌミチ』を連想しました。
万田:あそこは『イヌミチ』と同じところをもう一度使わせてもらっているんですけど、これは予算的な問題というのがすごく大きかったんです。最初の脚本の段階ではもうちょっと洋風の、廃屋のようで別室に居住スペースがあるガレージみたいなところを想定していたんですけど、なかなか予算との折り合いがつかずに『イヌミチ』のときに大変お世話になったところにまたお願いをしたんです。なので、日本家屋であることにものすごく意図があったということはなくて、いまだにあれが日本家屋だったことがいい方向に転んでいるかそうでないかは自分でもよくわからないですね。現代的なテーマであったり装置だったりを扱いながら、やっている場所が日本家屋というのはすごく違和感があると思いながらやったんですよね(笑)。その違和感がいいのではないかと言う人もいるんですけど、観た方がどんなふうに思われるかはわからないところはありますね。
- ※3:宮本なつさんが自ら企画し主演をつとめた短編映画(旧芸名の「斉藤夏美」名義)。宮本さんの出身地である群馬県藤岡市が舞台となっている。2014年開催の第8回田辺・弁慶映画祭でグランプリ・市民賞・女優賞・男優賞の4冠を獲得したのをはじめ各地の映画祭で高評価を得て2015年にテアトル新宿で公開された。
「相変わらず恋愛映画ですよね。男女の愛の映画を作ったつもりです」
―― 今回は、先ほどからお名前も出ている小出豊さんと、『みちていく』(2014年)の監督で立教大学で監督がご指導された竹内里紗さんとの3人で脚本を書かれていますが、3人で書くというのはどのような経緯で決まったのでしょう?
万田:小出くんは、自分で監督した『こんなに暗い夜』(2009年)という映画のあと、あまり映画の仕事に関わることがなかったので、なにかの機会があれば一緒にやってほしいなというのはずっと思っていたんです。それで今回、映画を作ると決まったときに小出くんに脚本を書いてもらおうと最初から思っていました。竹内は、当時は立教大学を卒業したてで藝大の院(東京藝術大学大学院映像研究科映画専攻監督領域)の1年生で、立教大学時代に作った『みちていく』がとても面白かったので、まだプロの仕事をやったことがない竹内に仕事を振ってなにかをやらせたいなという想いはありましたね。これもかなり早い段階で竹内も混ぜて3人で作っていこうというのは決めていました。
―― 小出さん、竹内さんと一緒に脚本作りをやって発見したことというのはありますか?
万田:改めて発見ということはあまりなかったかな(笑)。ただ、最初に話した兄嫁の話で「こんな感じで」というのを小出くんに振ったときに、彼がものすごく暗くて意地悪なプロットを書いてきて「ああ、小出くんは相変わらず暗いな」って、発見というよりは確認しましたね(笑)。竹内は、最初のころの打ち合わせには参加していたんですけど、藝大の自分の課題が忙しくなったりして、具体的なプロットができてホンができたあたりで1回ちょっと離れたんです。そのあとにまた入ってきたので、主に後半の家に行ってからのお母さんと長谷川とのやりとりとかを書いてもらったりしました。ただ『みちていく』とあまりに内容的に違う映画なので、やりにくそうなところはあったみたいでしたね。
―― 監督と小出さん、小出さんと竹内さんはそれぞれ10数歳の年齢差があって、ある意味で3世代のようなところがあると思いますが、それは組むにあたって意図はされていたのでしょうか?
万田:ああ、あんまり意識したことはなかったですけど、たしかにそうなってますね(笑)。ただ、小出くんとも竹内とも、美学校周りの映画を観たり話したりをずっとしてますし、一緒にご飯を食べに行くこともあるし、世代が離れているという感覚はぼくにはなかったですね。だから、特に若い人の感覚が欲しいから組んだとか、そういうことは全然ないです。
―― 『シンクロナイザー』は立教大学の「新しい映像環境をめぐる映像生態学研究の基盤形成」という研究プロジェクトで製作されて、監督の前作の『イヌミチ』は映画美学校の高等科コラボレーション作品でした。商業映画と違う成り立ちの長編を2作手がけられてきましたが、制作の過程で商業映画との違いを感じるところはあるのでしょうか?

万田:作り方自体はそんなに変わっていないですね。今回も研究プロジェクトという名目にはなっているんですけど具体的には商業的な映画作りと変わらないプロセスで、ただお金が少ないっていうことですよね(笑)。そうすると、一番比重を占めるのは人件費でスタッフも最低限の人数が必要ですから、まあ「申し訳ありません、ギャラ少ないんですけど」と頼んで(笑)。でも、これも低予算の商業映画でよくあることですから、ぼく自身は違いは感じていないし、美学校だからこう、立教だからこうというのは感じていないし、逆に今回は最初に立教大学のロゴが出る映画だから絶対にベッドシーンをやろうと思ったりはしましたね(笑)。
―― ベッドシーン以外にも、文部科学省も絡んだプロジェクトの映画にこんなカットがあるのかというところもありましたが(笑)、大学のプロジェクトということで内容に条件などはなかったのでしょうか?
万田:それは全然なかったです。だから、商業作品の場合はプロデューサーが作品に対して「ここはもうちょっと」とか、あるいは役者さんのイメージがあるからこれはできないとかもあるので、むしろそういう意味では逆に枷はなかったのかもしれないですね。
―― 『シンクロナイザー』は、記事などで「サイコスリラー」のように紹介されることもありますが、監督ご自身はカテゴライズとしてはどういう映画だと考えられていらっしゃるのでしょうか?
万田:ぼくは毎回そうなんですけど、相変わらず恋愛映画ですよね。男女の愛の映画を作ったつもりです。それは下敷きにした『ザ・フライ』がそうなので『シンクロナイザー』も男女の恋愛映画です。
―― ジャンル映画的な手法を用いつつ、ある意味で既存のカテゴライズに当てはまらないという点で、同じ立教大学のプロジェクトで製作された篠崎誠監督の『SHARING』(2014年)や、プロジェクトとは無関係ですが黒沢清監督の『クリーピー 偽りの隣人』(2016年)と共通するものがあるようにも感じました。
万田:ああ、特にお互いに影響されているわけではないですけど、やっぱり好きな映画が共通していたりするので、そうすると共通するテイストというのが出てくるのかもしれません。そういうテイストの出方がストレートになってきているところはあるかもしれないですね。
―― では最後に、記事を読まれる方に向けてメッセージをお願いします。
万田:ぼくの映画は毎回売りが難しいというか、見るからに「これ面白そう」とか「楽しそう」とかいうのがないんですけど、観た方は必ず「面白かった」と言ってくれているんです。なので、とにかく観てほしいです。「観れば絶対に面白いので観てください」という、それだけかな。「こういうふうに観てください」みたいなことはまったくないですね。ただ、観ると「わあ、変なものを観た。でもやっぱりすごく面白かったな」みたいなところなので、ぜひ観ていただきたいと思います。
(2017年1月20日/ユーロスペースにて収録)
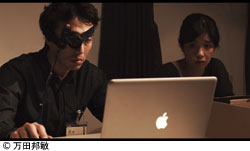
シンクロナイザー
- 監督:万田邦敏
- 脚本:小出豊 竹内里紗 万田邦敏
- 出演:万田祐介 宮本なつ 古川博巳 中原翔子 大塚怜央奈 美谷和枝 ほか
2017年2月11日(土)よりユーロスペースにて公開

